2024-25シーズンから「第2フェーズ」に突入する、国内トップリーグ「リーグワン」。
その未来像として、試合数の増加、スタジアムの固定化、海外チームとの交流、地域密着型の育成体制など、数多くの新方針が発表されました。
しかし、公式発表の内容は「専門的」であり、文章やファイルの「読み辛さ」やなど、非常に分かりにくいと感じたファンも多くいたと思います?
本ブログでは、ファン目線でわかりやすく、今後のリーグワンの方向性やシーズン構成の変更点、ラグビーの魅力がどう進化していくのかを詳しく解説したいと思います。
「リーグワンは何処へ向かっているのか?」そして、どう変わっていくのか?
興味のある方は、続きをご覧ください。
リーグワン(2024-25シーズン以降)今後の方向性
1. ファンの皆さまに最高の競技力を通して、感動体験を得て頂く
スタジアムの固定化とホーム&アウェー制の導入
- 2025 – 26シーズン 以降、ルール整備によりスタジアムの固定化とホーム&アウェー制を強化
- ファンが本拠地スタジアムで、選手の魅力にふれる機会を広げる
普及育成枠の導入
- 育成強化のため、一定数の「カテゴリA」選手に、日本での義務教育経験を要件とする
- 多様な実力選手の連携による感動を持続的に高める
2. より多く、より長く、より多様な試合を、ファンの皆さまに楽しんで頂く
試合数の拡充
- 2024 -25シーズン は、ディビジョン1の試合数を「18試合」に増加
- 全体試合数も(173試合 → 223試合)へ拡大
秋春制の導入に向けた準備
- 2028 – 29シーズン からの「秋 〜 6月」開催を目指し整備を進行
- 試合数の段階的増加もあわせて検討
海外連携の推進
- 2026 – 27シーズン 以降、国際大会形式の導入と海外チーム参入を協議
(クロスボーダーや海外チームの招致)
3. ラグビーを通じてチームワーク人財に成長する楽しさと喜びを、多くの皆さまにお届けする
地域と連携した育成強化
- アカデミーやスクールを通じて、地域の普及活動と連携し、青少年の育成を推進
チームワーク育成のプログラム化
- 選手・ファン・企業・地域が協力し、人材育成とチームワークを深める仕組みを展開
4. チーム・リーグ合計で、事業規模を550億円規模に拡大 2027-28シーズン
自主財源と地域投資の拡大
- 興行収入や協賛などの自主財源を拡大し、地域支援への投資を強化
協賛比率の適正化
- 母体企業の協賛比率をディビジョン1平均で60%以内に抑え、事業の安定性を確保
サラリーキャップ導入(2027-28シーズン目標)
- サラリーキャップ導入を検討し、リーグの魅力と安定性を高める
フェーズ別展開イメージ
| フェーズ | 期 間 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 第1フェーズ | 開幕年 〜 2023-24 | 基盤整備 |
| 第2フェーズ | 2024-25 〜 2027-28 | 試合・体制・育成の拡張 |
| 第3フェーズ | 2028-29 〜 | 世界最高水準の実現と国際展開へ |
第2・第3フェーズで目指す姿
秋からの「若手育成リーグ」開催を目指す
スタジアムの固定化
今まで以上の「ホスト&ビジター」を推進
総事業規模は前年度からの550億円を目指す
段階的な試合数増加を検討
海外チームとのチャンピオンシップやリーグ参入を招致
サラリーキャップの導入を目指す
ディビジョン1のチーム数は「12 or 10」
リーグワンの秋開催を目指す
総事業規模は650億円を目指す
(母体企業への依存度を下げる)
将来的な試合運営・制度の方向性(抜粋)
スタジアム要件(2028-29以降)
上位ディビジョンに昇格する際に必要な条件です。
ホストエリア:活動拠点(スタジアム、練習場、クラブハウス)が所在する地域
セカンダリーエリア:チーム・母体企業の所縁のある地域
ホストスタジアム:ホストエリア内(3ヵ所が上限)のスタジアム
セカンダリー:カンダリーエリア内のスタジアム(上記の所縁のある範囲で、複数設定が可能)
キャパ:ディビジョン1(収容人数1万人以上)・ディビジョン2 / 3(2,500人以上)
試合実施の割合:ホストで5割以上を開催
ホスト+セカンダリー:合計で8割以上
まとめ
まぁ、未来妄想図なので・・・
まず、ホスト(スタジアム)の固定に関しては、ますます関東での開催が増えてしまう。
別に、パナソニックとクボタが仙台で対戦したり、12チームが主要会場をツアーした方が面白くないかな?
大阪市内(長居公園)には、公式戦ができる会場が3つもあるのだから、2日で6試合も可能です!
一枚のチケットで、1日3試合をハシゴ観戦できたら楽しくないですか?
観戦初心者を楽しませる事こそが、「感動体験」では無いのだろうか?
育成に関しては、早急に開始した方がと思います。
ですが!
そもそも、新人選手の多くは即戦力として入団しているので、育成メインの「セカンド リーグ」ではなく、リーグワン開催期間外に「もう一つのリーグ」を設立するべきだと思います。
私が以前から訴えている、「国内2リーグ制」です。
日本人を限定にした、出場機会の少ない若手とベテラン、入部を希望するフリー選手が集まり、2か月程度の短期リーグを開催する。
滞在費用や報酬などの問題はありますが、発表された育成リーグでは、結局チーム企業の負担が増えるだけ。
外国人選手に経験値を積ませるのための、「予備リーグ」になる恐れが高いと思います。
試合数の拡充に関しては、同じディビジョンでも実力の差が大き過ぎませんか?
これ以上、勝敗が予想できる試合を増やさないでください。
やるなら、「ディビジョン1」を8チームに減らして、3回総当たり(21試合)を望みます。
海外の連携?
メジャーリーグラグビーやスーパーラグビーと日程が近いので、チャンピオンシリーズなんて面白いと思いますが、外国人選手枠を統一しないと成立しないですよね!
海外チームを招致するなら、消滅したハグアレスXV(アルゼンチン)や、欧州で途方に暮れているブラック ライオン(ジョージア)が面白いかも!
事業規模の拡大に関して思うことは・・・
なぜ、右肩上がりを目指すのだろうか?
プレミアシップもスーパーラグビーも縮小しているのに・・・
そして、サラリーキャップの件ですが、社会人選手とプロ選手が混合するリーグに、全チームが公平となるルールを導入できるのだろうか?
私から最後に、
別に上を目指すのは悪い事ではありませんが、上を見過ぎると足元が見えなくなります。
未来への目標よりも先に、現状の環境整備の方が大切だと思いませんか?
私は、会場に行っても、テレビ中継を見ても思うことはいつも同じです。
それは、ゴールポストが低い!
そして、トライエリアの後方が人工芝で危険!
最高峰を目指すリーグが「この競技場」で試合をして、何とも思わないのだろうか?
特に、人工芝は改善して欲しいです。
毎年、芝生がズレて選手が滑る姿を見ています。
絶対に危ない!
本来なら、中央付近に飛び込んでトライしたいけれど、人工芝の上で飛び込むと怪我する恐れがあるので、ゴール隅みにグランディングする外国人選手の姿を頻繁に目にしませんか?
観客が沸く「ダイビングしてトライ」するシーン。
人工芝が原因で、失っていませんか?
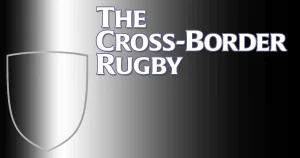
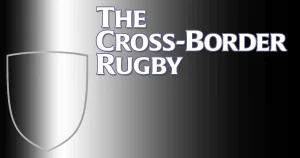
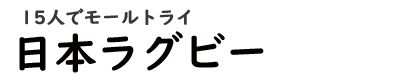

コメント