2025年2月15日に行われたリーグワン第8節「トヨタ自動車 vs 静岡ブルーレヴズ」の一戦。
スコアやプレーの内容とは別に、ある驚きを感じました。
それは、「本当に正しいの?」と思わず疑ってしまうような、今の日本ラグビーの現状です。
スターティングメンバーに名を連ねた外国出身選手の数は、両チーム合わせて実に23人。
全出場選手46人のうちの半数を占めていた。
今なお社会人リーグ時代の雰囲気を色濃く残す日本のラグビー界にとって、理想的な姿と言えるのでしょうか?
日本人選手の居場所を奪う「オーバーフォリニズム」
この試合で特に印象的だったのは、静岡のスタメンに10人の外国出身選手が含まれていたことです。
そして、伊藤選手の負傷による一時交代でショーン ヴェーテー選手がピッチに登場し、静岡の外国出身選手は合計11人になりました。
当然ですが、静岡には4人の日本出身選手しかいなかったことを意味します。
対戦相手のトヨタ自動車も、先発に8人・控えに3人の外国出身選手を起用しており、両チームあわせて登録選手46人中23人が外国出身選手という状況でした。
50パーセントが外国出身選手だったのです。
日本ラグビーの未来は、「これが現実」となるのだろうか?
国内育成や日本人選手の出場機会に対して、「強い危機感」感じました。
まさにこれは、“Overforeignism(オーバーフォリニズム)”=外国出身選手の過剰依存状態と呼ぶべきではないのでしょうか?
このままでいいのか?リーグと日本代表のジレンマ
- プロとアマチュアの混在
- 地域密着
- 日本代表強化
しかし、多くのチームが即戦力として外国出身選手を頼りにしている。
野球やサッカーと比べると、ラグビー界ではトップクラスの選手であっても、数千万円程度で獲得できるケースが多いんです。
もちろん、外国出身選手の活躍がリーグの競技レベルを押し上げているのは間違いない。
ですが一方で、日本人選手が実戦の場を奪われ、成長の機会を失っている現実に注目してほしいです!
ただでさえ、試合数が少ない日本の環境では、今後プロ契約を選ぶ選手が減るのでは?と不安を感じます。
以前の記事にも書きましたが、この状況が続けば「代表は強化され」「日本人は衰退する」・・・
協会やクラブチームは、「結果的に日本代表が強くなるなら、日本人が居場所を奪われても仕方がない」とでも思っているのだろうか?
はっきりとした正解があるわけではありませんが、「ラグビーが日本のスポーツ文化」として継続するためにも、多くの日本人選手が活躍できる環境を確保するべきだと考えます。
フランスのJIFF制度との違い
Joueur Issu des Filières de Formation(フランス育成システム出身選手)
この制度は、フランスのクラブに3年以上所属している選手が対象となりますが、23歳までに資格を取ることが義務付けられています。
そして、この資格を持つ選手が、登録メンバー23人中16人以上になることが厳格化されているのです。
最大の目的は、外国人選手の比率を抑え、フランス育成選手の出場機会を確保するためのルール。
試合終了後は、適切にルールが守られているか出場選手の割合が公表されます。
下記は実際に公表されているデータです。
(スタメン15人中11人がフランス育成選手、4人がアメリカやオーストラリア出身選手)
ベンチ入り6人(26%)の中には、日本代表の斎藤直人選手も含まれています。
Match Toulouse vs Vannes, 01/03/2025
先発メンバー15
11人(73%):フランス育成のJIFF選手(プロ or アカデミー)
4人(27%):JIFF条件を満たさない外国人選手
0人:アカデミー所属の外国籍選手
ベンチ入りを含む23人
17人(74%):フランス育成(JIFF)選手
6人(26%):JIFF条件を満たさない外国人選手
0人:アカデミー所属の外国籍選手
リーグワンにも、「カテゴリA」選手が17人以上出場のルールに似ていますが・・・
似ていますが、実際に出場している人数が全く異なります。
日本のカテゴリで例えるなら?
- 「カテゴリA」=「フランス育成(JIFF)選手」
- 「カテゴリB」=「アカデミー所属の外国籍選手」
- 「カテゴリC」=「JIFF条件を満たさない外国人選手」
日本では、「カテゴリB」選手の出場が40%以上を占めていますが、フランスでは多くの試合が「0%」です。
また、「カテゴリA」に当たる「JIFF」の資格を得るためには、最低でも19歳の夏までにはクラブチームに所属する必要があるので、日本とは全く異なる制度だと言えます。
まとめ|オーバーフォリニズムの先にある、日本ラグビーの未来
近年のリーグワンでは、多くの外国出身選手が登録メンバーに名を連ねるという現状。
これは一時的な現象なのか?
それとも、今後さらに進行するのか?
ラグビー協会やクラブチームは、「強化」だけを求めず「進化」を追及して欲しい。
そして、我々ファンの姿勢もまた、ラグビーの未来を左右する大きな要素だと思います。
「勝てばいい」「強ければそれでいい」と、短期的な結果を求めるのではなく、日本人選手が育ち、チームの躍進を担っていく過程を楽しむことが、ラグビー界全体の相乗効果だと私は信じたいです。
最後に、「オーバーフォリニズム」は単なる造語ではない。
それは、日本人選手の存在価値と将来に対しての「警告のサイン」です。
- 山下 憲太 A
- 日野 剛志 A
- 伊藤 平一郎 A
- ジャック ライト B
- マリー ダグラス A
- ヴェティ トゥポウ A
- クワッガ スミス C
- マルジーン イラウア A
- 北村 瞬太郎 A
- サム グリーン A
- マロ ツイタマ A
- ヴィリアミ タヒトゥア C
- シルビアン マフーザ A
- ヴァレンス テファレ B
- 山口 楓斗 A
- 作田 駿介 A
- 河田 和大 A
- ショーン ヴェーテー A
- 大戸 裕矢 A
- シオネ ブナ A
- 岡崎 航大 A
- 家村 健太 A
- 岡崎 颯馬 A
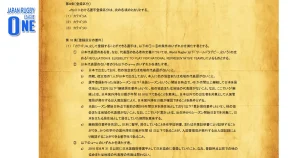
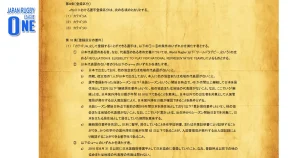
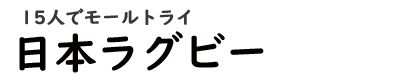

コメント