ファン離れが加速してきた?
「ラグビー離脱を合言葉に」――
長年応援してきたファンが、静かに離れていっているのは、もはや誰の目にも明らかです。
たとえば、6月の決勝戦では5万人以上の観客を動員しましたが、SNSでは「企業によるチケットばらまきが酷すぎる」との声が多く見られました。
2025年シーズンの平均入場者数は8,380人と発表されていますが、この中には企業動員が3割以上含まれていると想像がつきます。
もし、ファンクラブ優待や正規ルートでチケットを購入した観客だけをカウントすれば、観客数は平均5,000人を大きく下回っているでしょうか?
べつに、これが原因で退屈した訳ではありませんが・・・
今シーズンは生観戦「0」、生中継観戦も「ほぼ0」でした。
録画しても、倍速で「流し見」する程度なので、誰が活躍していたかもよく覚えていません。
退屈過ぎたリーグワン2025
やはり、ラグビー界における外国出身選手の多さには、どうしても目が行ってしまう。
実際、「純粋な日本人選手がたった3人だけ」という試合があったほどです。
野球やサッカーなど、多くの競技において外国人選手の存在は、日本人だけでは補いきれないポジションを支える存在であり、いわば“穴埋め”の役割として起用されるケースが多い。
日本人選手の活躍を奪うような補強ばかりでは決してない。
ところが、ラグビーにおいては事情が異なる。
高校でも大学でも、リーグに参戦するクラブチームにおいても、外国出身選手がポジションを奪い、日本人選手が活躍の場を失い、静かに引退していく・・・
そんな負のルーティンが、確実に存在しているのだ。
なぜ、外国人選手は増えるのか?
過去の記事でも触れましたが、実は毎年50人以上の外国人留学生が日本の大学を卒業しています。
彼らは帰国せず、日本国内のリーグに進む道を選ぶケースが多く、各チームもその受け入れに積極的です。
では、なぜそれほどスムーズに受け入れられるのでしょうか?
その理由はとてもシンプルです。
大学でプレーする留学生たちは、入学前の段階からすでに学校側の厳格な選抜を経ており、能力や体格はもちろん、日本での生活適応力など多くの基準をクリアしています。
そのため、素行不良やトラブルを起こすリスクが非常に低く、チームにとっても安心して迎え入れられる存在となっているのです。
あまり大きな声では言えませんが、スーパーラグビーやヨーロッパの主要リーグの関係者からは、
「これほど簡単に契約できるリーグは他にない」と、日本のリーグが見られているのが現実です。
残念ながら、それは日本のリーグの競技レベルや契約基準が、国際的な水準と比べてまだまだ低いと評価されていることの裏返しでもあるのです。
もうお分かりですよね!
プロ野球でたとえるなら、かつての「読売ジャイアンツ」が分かりやすい例です。
毎年のように他球団からフリーエージェントでエースや4番打者を獲得し、さらに大物外国人選手まで迎え入れる――潤沢な資金を武器に、他球団が対抗できない圧倒的な戦力を築いていました。
一方、ラグビーでは状況が異なります。
選手の年俸はプロでも2,000万円程度、社会人選手なら数百万円でも獲得できるため、優秀な外国人選手を各チームが現実的に補強できてしまうのです。
本来なら大きな戦力差があるはずのチーム同士でも、「外国人選手の起用人数」に限ってみれば、ほとんど横並びの状態になっています。
どのチームも他に遅れまいと、スタメンに10人以上の外国人選手を並べる――そんな競い合いが起きており、結果として“起用バランスの均衡”だけが保たれているのです。
これこそが、今の日本ラグビーの現実といえます。
では、どのチームにも外国人選手が多く在籍しているのに、なぜ毎年優勝争いをするチームと、入替戦の常連となるチームとに、ここまで明確な差が生まれてしまうのでしょうか。
世界的スターの参戦と日本ラグビーの特異性
サントリーのギタウ、神戸のダン カーター、ドコモにペレナラ・・・
ヨーロッパのトップチームでも主力として活躍できる超一流の選手が、日本のリーグに加わったことは、まさに衝撃的でした。
そして、そんな選手が「たった一人」チームに加わるだけで、戦力は一気に変わります。
特にバックスの9番・10番・12番といったポジションは、ゲームメイクの中心。
日本のラグビーでは、彼ら一人で試合の流れをコントロールし、完結させてしまうことすらあるのです。
私自身、ダン・カーターが神戸に加入すると聞いたときは、興奮で眠れないほどでした。
実際に彼のプレーを生で観戦した際、後ろの席にいた某大学ラグビーの監督がポツリとこう言ったのです。
「ダン カーター一人で、サントリーに勝てるな」――その言葉に、私も心から頷かずにはいられませんでした。
世界トップ選手が日本で力を抑える理由
直近のリーグでは、東芝が見事に2連覇を達成しました。
その中心にいたのが、ニュージーランド代表として2大会連続でW杯の背番号10を背負った名司令塔、リッチー モウンガです。
ただ、ここで疑問が湧きませんか?
ワールドラグビーの「ベスト15」に選ばれるような世界トップクラスの選手が・・・
なぜ、アマチュア選手がプレーする「日本のリーグ」を選ぶのだろうか?
たとえるなら、大谷翔平選手が高校野球に出場しているようなもの!それほどまでに、実力の差があるのです。
長年、ニュージーランド代表やクルセイダーズでプレーしていたモウンガを見てきましたが、日本で手を抜いているようには感じません。
それでも、明らかにプレーのテンポや展開は遅くなっているように見えます。
実際、ニュージーランドのスポーツサイトでも「モウンガのパフォーマンスは明らかに落ちている」と報じられていました。
おそらく彼自身が、本来のプレースタイルを抑え、日本の選手たちやリーグのリズムに合わせてプレーしているのでしょう。
ただ、世界トップクラスの司令塔に、こうしたプレーを求めざるを得ない日本のリーグの現状には、正直なところ残念さを感じずにはいられません。
なお、モウンガの契約は2026年シーズン終了までと報じられています。
外国人に奪われる伝統的ポジション
以前はロック(4番・5番)に外国人選手がいることが当たり前でした。
日本代表が南アフリカを破った2015年のシーズン開幕戦「パナソニック vs サントリー」では、両チーム合わせて7人の外国出身選手がスタメンに名を連ねました。
ですが、今期の開幕戦「パナソニック vs サントリー」では、12人がスタメンに・・・
あの頃は、スクラムの1列に外国人選手がいるだけでも「珍しいなぁ」と感じたものです。
ところが今期の決勝戦では、後半の時間帯に5人もの外国人選手が並んでいました。
スクラムハーフにも同じことが言えますね!
日本代表の強化と競技人口減少の矛盾
これまで日本人が当たり前のように担ってきたポジションも、体格や能力に優れる外国出身選手との争いになれば、多くの場合「日本人が負けてしまう」のが現実です。
そして、そのポジションを勝ち取った外国人選手は、やがて日本代表資格を得て「代表の座」までも奪っていきます。
確かに、彼らの存在によってクラブチームは強化され、日本代表も強くなる「一見すれば “ウインウイン” 」の関係に見えます。
しかし、実際にはどうでしょう・・・?
日本人のラグビー競技人口は年々減少している中で、日本人の活躍の場そのものが奪われていく。
これこそまさに「負のウインウイン」ではないでしょうか。
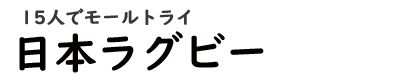

コメント