ラグビー代表チームは、出生国以外の要素(親の国籍、所属年数、居住歴)によって、選手を編成するのが一般的となっています。
ですが! もし!!
「代表資格は出生国」と厳密に定められた場合、現在の世界ランキングは大きく変動することは間違いないですよね!
今回は、2023年フランスW杯の登録メンバーを参考にしながら、代表資格を「出生国のみに限定」した場合の影響度・得失を考えてみました。
俺的な妄想記事です・・・
外国出身選手ゼロは2ヵ国のみ
2023年ラグビーワールドカップに出場した上位10ヵ国のうち、スコッドにも登録メンバーにも外国出身者が一人もいなかったのは南アフリカとアルゼンチンのみ。
つまり、両国には「出生国ルール」になった場合でも全く影響を受けません。
ここで思うことは?
南アフリカには、国際プロリーグに参加するクラブチームと、国内トップリーグも存在し、ジュニアの育成や年代別代表の強化にも力を入れています。
当然、南アフリカの国籍を持つ多くの選手が経験を積み、国内リーグから国際リーグ、そして代表へのステップアップを目指せる最高のシステムがあります。
これは、ニュージーランドでもフランスでも同じ事なのですが・・・
一方のアルゼンチンは?
国内プロリーグは無く、主にアマチュア選手が参加する2つの地域リーグが活動。
また、スーパーラグビー除外後に編成された「ハグアレスXV」は、戦力分散のため「ドゴスXV」と「パンパス」の2チームに分けて、北中米の国際プロリーグに参戦しています。
ですが、このプロチームには現役代表選手は一人も所属しておらず、全ての選手が海外のリーグでプレーしているのです。
国内では十分な経験も報酬が得られないため、代表クラスの選手たちは若くして欧州へ移籍します。
アルゼンチン代表は、「選手を国外に送り出すこと」を前提とした強化モデルを構築しており、「出生国のみ代表資格」という条件に最も忠実でありながら、世界の強豪と互角に戦える数少ない国の一つだと言えます。
北半球の強豪国に甚大な影響
最も大きな影響を受けるのがアイルランド・イタリア、そしてスコットランドです。
これらの国々では、南アフリカやニュージーランドなど他国にルーツを持つ選手が多数代表入りしており、その多くが出生国以外の資格でプレーしています。
アイルランドは、国内の育成システムと欧州リーグの競争環境に支えられた強豪国ですが、出生地に限定した代表資格になると、主力選手の多くが選出できなくなり、大幅な戦力ダウンが避けられません。
イタリアは国内リーグが活発で、将来の代表候補となる選手層も厚い一方、ユナイテッドに参戦している2つのプロチームには、多くの未代表の外国人選手が所属しています。
その中には、将来の代表入りを目指す選手だけでなく、すでに代表としてプレーしている選手も多く含まれています。
スコットランドも同様に、国外にルーツを持つ「スコティッシュ・クオリティ」の枠が大きく縮小し、スコッドのおよそ3割が代表資格を失う可能性があります。
過去2年間に主力として代表でプレーした、外国籍選手を紹介します。
アイルランド:ギブソンパーク、バンディー アキ、ジェームス ロウ(NZ)ビーラム、マック ハンセン(豪)ハーリング(南ア)マッカーシー(USA)
イタリア:ネグリ(ジンバブエ)ブレックス、ネメル(アルゼンチン)イオアネ(豪)バーニー(ウェールズ)カプオッツォ、パジェレロ(仏)ヴィンツェント(南ア)ディノ ラム(イングランド)ハラフィヒ(NZ)
スコットランド:スクーマン、ファン デル メルヴァ、カイル ロウ(南ア)アシュマン(カナダ)サム スキナー、ベン ホワイト、ハミッシュ ワトソン(イングランド)トゥイプロトゥ(豪)
南半球ではオーストラリアが最大の被害国に
オーストラリア代表は、トンガやフィジー系の選手やラグビーリーグ出身者など多様な背景を持つメンバーで構成されています。
出生国限定のルールが導入されると、戦力低下は避けられないでしょう。
一方で、ニュージーランドもトンガやフィジーにルーツを持つ選手を多く擁していますが、多くはニュージーランド生まれであり、出生地基準の代表資格であってもスコッドへの影響は比較的軽微にとどまると見られます。
トンガ・サモアなど島嶼国が台頭する可能性
これまで多くの選手が、母国ではなく「他国の代表」としてプレーする道を選んできました。
しかし、もし出生地に基づいて代表資格が決まるルールになれば、こうした選手たちが母国の代表に復帰する可能性があり、結果的に戦力の底上げにつながると考えられます。
そのため、トンガやサモアのように多くの選手を他国に輩出してきた国にとっては、上位国との差が縮まりテストマッチでの対戦機会も増えるのではないでしょうか。
日本代表は「最大の被害国」になる!
日本代表はこれまで、帰化や長期在住による外国出身の助っ人選手を積極的に起用してきました。
しかし、その多くが「日本にルーツを持たない」ため、出生国制限が導入された場合、確実にスコッドの半数以上を失う事態に陥ります。
また、トンガやサモアのように、他国で代表活動している選手は一人もいないため、プラスになる要素は1ミリもありません。
日本よりランキングが低い国々であっても、優秀な選手が他国の代表に選ばれたり、海外リーグで活躍している例は少なくありませんよね!
それに対して、日本人が海外リーグで大きな実績を残す例は少なく、国際舞台での競争力に課題があることが明らかになっています。


世界ランキングで「台頭」するのはどこか?
もし「出生国限定ルール」が導入された場合、これまで上位国に押されていたいくつかの国々が、大きく順位を伸ばす可能性があります。
とりわけ、サモア・フィジー・トンガといった太平洋諸国は注目!
これらの国々は長年にわたり、有望選手がニュージーランドやオーストラリアだけでなく欧州にも流出してきましたが、ルール変更により選手が自国代表へ戻れば、一気に戦力を高めることができます。
ジョージアは、上積みされる経験値は少ないものの、伝統的なスクラムの強さを武器にしており、上位国との差を大きく縮めるチャンスが広がります。
スペインやポルトガルは、多くの選手がスペインリーグで活躍し、代表チームも他国に頼らず自国選手を中心に構成されているため、マイナスになる要素は一切なし。
ロシアやルーマニアも注目すべき存在です。
ジョージアに次ぐスクラム大国として知られ、仮に全員が国内出身選手で構成されても、十分な戦力を維持できると思います。
ウルグアイとチリは、クラブチームと代表がリンクした、かつてのサンウルブズに似た活動をしています。
北中米リーグが活性化されれば、第二のアルゼンチンになる可能性がありますが・・・
旧ハグアレスXVの解体により、ウルグアイとチリのクラブチームには、未代表のアルゼンチン選手が多数在籍し、現行ルールでは数年後に代表入りする予定だと報じられています。
そして、スポーツ大国アメリカとカナダです。
幾度となく消滅してきた米国リーグも、メジャーリーグラグビー誕生により多くのアマチュア選手がプロに転向。
将来は二次リーグの発足も噂されています。
ラグビー人口世界一のアメリカと、多くの選手がアメリカでプレーしているカナダの躍進こそが、ラグビー不人気を救う存在だと思います。
結論:出生国ルールはラグビー界に何をもたらすか
「出生国のみが代表資格」という仮定のもとで各国代表チームの構成を見直した場合、世界のラグビー勢力図は大きく書き換えられることになります。
南アフリカやアルゼンチンのように、自国出身者のみでチームを構成できる国は例外であり、多くの強豪国が戦力を失う一方、これまで大舞台が設定されなかった国々にもチャンスが拡大すると期待できます。
アイルランド・スコットランド・イタリア・オーストラリア、日本といった国々は、外国出身選手に大きく依存しており、出生地ベースのルールが導入されれば深刻な戦力ダウンが避けられません。
特に日本代表は、自国にルーツのない助っ人選手が多いため、影響は最も大きいと考えられます。
一方、トンガ・サモア・フィジーなどの太平洋諸国は、これまで他国に流出していた選手たちが母国代表として戻ってくることで、戦力の大幅な底上げが期待できます。
現在の代表資格ルールは、常に上位国にとって有利に働いています。
そして、そのルールを決めているのも上位国が中心の組織であるため、自分たちに不利となるような改革が進む可能性はゼロに等しいです。
「代表の在り方」や「経済格差」、そして「ティア制度」など、ラグビー界が抱える根本的な課題に真剣に向き合い、変革に導くような存在が現れることを願いたいです。
そして、最後に北半球の補充問題
実は、トンガやサモアには「代表資格の問題」だけでなく、もうひとつ深刻な課題があります。
気づいている方もいると思うので、簡単に書きますが・・・
トンガやサモア出身の若手有望選手たちは、短期間の契約でフランスやイングランドのクラブに招かれています。
契約期間は、大半が1〜2か月程度です。
そして、この短期契約のオファーを受けるのは、多くが代表に初選出されたばかりの選手たち。
つまり、「即戦力」として補強が必要なクラブが、代表発表直後に目をつけて引き抜くケースが多いのです。
欧州では、ワールドカップ開催期間中でも国内リーグが中断されることが無いため、代表が抜ける欠員補充としての「引き抜き」が行われるのです。
新人選手の獲得には、時間を掛けて十分に調査しますが、代表スコッドに選ばれた選手であれば、調査なしでも「ある程度の実力」が期待できる。
そして、引き抜かれた選手たちは代表を辞退してフランスに渡ります。
何故、代表よりもクラブチームを選ぶのか?
答えはカンタンです。
もし、母国の代表に帯同しても、得られる報酬は数万円程度。
ですが、フランスに行けば1試合数十万円の報酬と滞在日数分の生活費が保証されるため、「この道」を選択する選手が減ることはありません。
以前、英国のジャーナリストが「1シーズン400万円を下回る契約」と報じていましたが・・・
2019年の日本大会直前、トンガは代表スコッドを発表した後に、複数の選手が代表辞退を申し出ました。
その結果、チームは本来の戦力を十分に揃えることができないまま、W杯本番を迎えることになったのです。


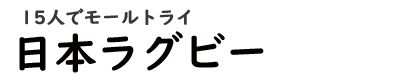

コメント